異常気象を追う
No.25
2009.02.25
吉野正敏
沖縄の雪・あられ・ひょう
失われゆく冬の異常低温
異常気象は起こらない方がよい。何事も平穏・平常に過ぎることが望ましい。このごろは冬の異常な低温がどうも起きないような気がする。暖冬ぎみに今年の冬もすぎようとしている。北海道など、北日本で豪雪の便りも聞くが、日本全体をみると、やはり平均気温は高い。
では厳しい寒さの冬は本当にこないのだろうか。この2月には春を過ぎて初夏の気温を観測した地点すら出現し、2月としては観測開始以来の高温であったと 報じられた。その後さすがにまた2月の平均状態にもどって、気温も降雪も積雪も例年のようになった。その振れの大きさに驚いた人は多かった。地球温暖化傾 向の冬とはこのようなものかと、実感した人は少なくなかったと思う。
日本は南北に細長い島国で、北海道の気候と沖縄の気候とはかなり違う。テレビが発達した今日、われわれは毎日、画面の風景でそれを知る。冬の寒さは北日 本がもちろん厳しいが、亜熱帯に近い沖縄は冬の寒さの南限に近いので、寒さの変動はかえって明らかに出るかも知れない。熱帯は温帯のように四季がないか ら、今の話の対象外だが、温帯もその南と北では違いがどのようになっているのか、その一端を紹介したい。
沖縄の冬の異常気象
沖縄気象台が編集した『沖縄気象台百年史(1992)』の資料編によると、沖縄の災害はもちろん夏秋の台風・春夏の干ばつがひどい。いま、冬の異常気象 に注目したいので、雪と雹(ひょう)の記録を江戸時代以来拾ってみた。ひょうの記録のなかには、4月・9月や月が不明の場合もあるが、一応、ふくめた。そ の結果は(表1)のとうりである。
(表1)沖縄の雪とひょうを観測した年
| 年月日 | 雪 | ひょう |
| 1721年9月 | ― | ○ |
| 1726年3月 | ― | ○ |
| 1727年 | ― | ○ |
| 1741年 | ― | ○ |
| 1741年 | ― | ○ |
| 1770年4月6日 | ― | ○ |
| 1774年 | ○ | ― |
| 1805年2月2日 | ― | ○ |
| 1816年1月7日 | ― | ○ |
| 1843年3月 | ○ | ― |
| 1845年2月 | ○ | ○ |
| 1857年1月 | ○ | ― |
| 1865年 | ― | ○ |
この(表1)によると、1・2・3月に多いことがわかる。また、ひょうは1720年代に多く、1750年代・1760年代にはなく、1770年代からま た多くなり、1780年代・1790年代にはなく、その後、多くなり、1860年代まで続いた。このように、20年くらいの記録のない時代を含みながら、 18世紀から19世紀前半に雪やひょうによる災害が頻発した。
この18世紀から19世紀前半は北半球全体に低温な時代で“小氷期”とよばれている。沖縄の災害の発生にもその時代の影響がはっきりでている。これは、後で述べる小氷期の冬の季節風活動の長期変動と関係していると考えてよかろう。
もう一つの資料を紹介しよう。木崎甲子郎編『琉球の自然史』(築地書館)によると、10年ごとにまとめた琉球の寒冬の記録は(表2)のとうりである。
(表2)琉球の1720年~1880年の10年ごとに区切った期間における寒冬の記録
| 年代(10年ごと) | 記録回数 |
| 1721-1730年 | 2 |
| 1731-1740年から1781-1790年まで | 0 |
| 1791-1800年 | 1 |
| 1801-1810年 | 3 |
| 1811-1820年 | 1 |
| 1821-1830年 | 2 |
| 1831-1840年 | 0 |
| 1841-1850年 | 2 |
| 1851-1860年 | 2 |
| 1861-1870年 | 2 |
| 1871-1880年 | 4 |
この(表2)によると1721年から1730年2回のあと60年間は0、18世紀末から増え、19世紀前半の多発期を経て19世紀後半の極を迎えた。 (表1)と比較すると、1720年代に始まり、その後数十年には低温や雪による災害の記録はなく、18世紀の末から19世紀前半に急増したことはほぼ一致 している。
あられ(霰)とひょう(雹)
あられは氷の粒の降水で、雪あられと氷あられがあるが、沖縄で降るあられはほとんど氷あられである。冬、優勢なシベリア高気圧が南東方向に勢力をのば し、東アジアにその1部が張り出し、沖縄はその支配下にはいり寒波襲来となる。雄大積雲や積乱雲(入道雲)が冬といえども発達し、時おり局地的にパラパラ とあられが降る。このとき、地上の最低気温は約9℃以下で、風が強く、体感気温は低く、日中でも寒い。沖縄本島では1955年から1990年までの36年 間にあられは19回降った。あられが降る季節は冬で(表3)に示すように1月が最も多い。
(表3)沖縄(本島)におけるあられが降った回数と日数
| 月 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 回数 | 3 | 11 | 9 | 3 |
| 日数 | 5 | 19 | 14 | 3 |
1回の寒波であられが降る日数は、1日が15回、2日が8回、3日が2回、4日が1回である。南大東島でも1963年1月、西表島でも1985年3月にあられを観測した。これらの年は本州でも厳冬であった。
ひょうは氷のかたまりが降る現象で、一般には積乱雲にともなって降る。したがって、暖候季にも降る。沖縄各地において上記の期間とおなじ1955年から1990年の36年間に14回、降ひょうがあったが、そのうち9回は1月・2月・3月であった。
冬の季節風と沖縄
冬の季節風が吹き始めると、沖縄では風速は10-13m/sになり、ときには17m/sを超す。この風は東シナ海を吹き渡るあいだに海面から加熱され、水蒸気を補給され、大気は不安定になる。曇りや小雨の天気が続く。
特に低温な寒気が吹きだすと、あられ・ひょう、まれにみぞれをともなう。寒気の吹き出しがおさまり、シベリア高気圧の1部はちぎれて、移動性の高気圧と なって沖縄を覆うようになると、おだやかな天気となる。しかし、夜間、晴れて放射冷却が進むと、まれには結氷・霜をみることさえある。これらは、沖縄では 異常低温の場合だから、上述のように頻度は高くない。
2月の終わりになると、季節風は次第に弱くなり、揚子江下流域で低気圧がよく発生し、移動性高気圧と気圧の谷が沖縄に交互にやってくる。沖縄では昔から 〝ニンガチ・カジマーイ“(2月風廻り)とよび、旧暦の2月に海が荒れる日があり、漁師に恐れられていた。(図1)は3月16日から26日までの毎日の 気圧と降水量の日別平均値の変化を示す。この図は3月21日にきわだって気圧が低く、このころに低気圧の通過や前線が通過しやすいことを物語っている。
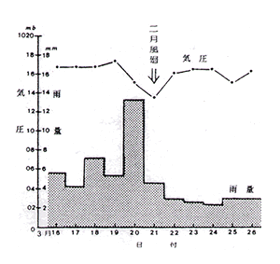
(図1)沖縄における“ニンガチ・カジマーイ”(2月風廻り)ころの 気圧と雨量の日別平均値の推移。[沖縄気象台(1992)による]
近年、船舶通信の技術向上による気象情報のいかし方が適確になってきたため、海難事故は少なくなってきている。しかし、東シナ海では強い冬の季節風の場 合、波の高さは4ないし9mに達し、かなり強い場合には9ないし14mになることもある。(図2)は1990年の月別海難発生数を示す。一般船舶は台風期 の8月に極大となり11月まで多い。しかし、注目しなければならないのは、漁船の海難事故が12月・1月に大きい値を示し一般船舶より1.5倍から2倍も 多いことである。
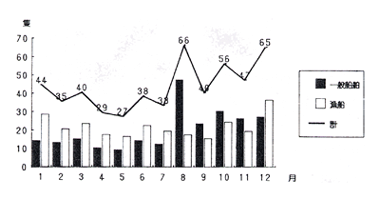
(図2)沖縄における海難事故の発生数の月変化、1990年。[沖縄気象台(1992)による]
異常気象発生の異常傾向を知ろう
最初に書いたように、異常気象は起こらない方がよい。それは確かである。30年に1回とか、数十年に1回とか、極めてまれに起こるから“異常な”気象な のだが、統計学的に言えば、30年に1回起こる値はでて当然である。見方を変えれば、統計学的に起こるべき値が、百年以上ももし実際に起こらなければ、む しろ、それが問題である。
沖縄の異常低温を調べてみて、それを強く感じた。18世紀末から19世紀前半に頻発した異常低温による現象がほかの期間には見られない。最近も見られな い。ある現象がどうして発生したかの研究はしやすいが、どうして発生しないかの研究は難しい。とにかく異常な傾向であることを指摘しておきたい。地球温暖 化―冬のシベリア高気圧の弱化―東アジアの冬の季節風の弱化―沖縄付近の異常低温の発生鈍化などなど、考えられるが、異常傾向をまずさらに明らかにしなけ ればならない。



