異常気象を追う
No.2
2008.04.09
吉野正敏
降水量の長期変動
年降水量
地球温暖化によって、気温の状態はどうなっているか、前回の[1]に紹介した。今回は降水量について述べたい。
“気候変動に関する政府間パネル、IPPC”が2007年にまとめた結果では、1900-2005年の期間における全地球の陸域平均年降水量の変動は(図1)に示すように、1950年代を中心に大きなピークをもつ波があり、次いで1970年代前半、1990年代後半、1920年代前半などに小さいピークがでている。波の下の方(降水量の減少期間)に注目すれば、1990年代前半、1910年代前半が明らかである。この図は7種類の解析結果を棒グラフ1種と色わけの折れ線6種でしめしているが、いずれも上記の傾向を示している。陸域の年降水量に関する限り、近年の温暖化の影響は認められないと結論してよかろう。
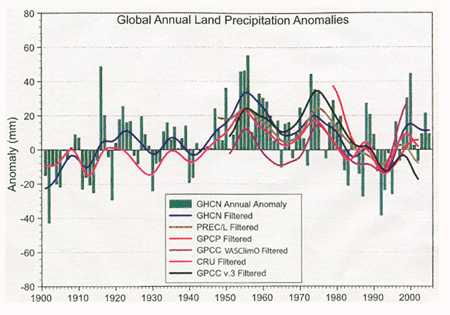
(図1)1900‐2005年における全地球陸域降水量の変動。平均値からの偏差で示す。( IPCC, 2007 による)
豪雨日
次いで、全世界の陸上における降水特性の変化を紹介しよう。(図2)(a)は1951年から2003年までの期間における“非常に強い豪雨日の降水量が年降水量に占める割合”の長期傾向を示す。アメリカ・ヨーロッパ・インド・中国・日本などでは水色(+1)、すなわち弱いながら増加を示している。(b)はそれを全球についてまとめて経年変化をみたものである。茶色の線は十年から数十年の周期変動を示す。1970年ころの極小期から1990年代後半へかけての増加傾向が明らかである。(図2)(a)に見るように西アフリカ・東アフリカ・西南日本・イギリス南部・オーストラリア南西部など地域的に減少傾向も認められる。これらの地域性が生じる理由の説明は現在のところ難しい。おそらく、赤道低圧帯・中緯度高圧帯の長期変動と、それにともなう熱帯地方の貿易風循環系の長期変化、熱帯低気圧の活動などが関連していると思われる。今後の研究を待つよりほかない。全世界的には、データのある限りの地域でみて、増加(+の地域)がまさっているので、(b)に示すような変化傾向となる。
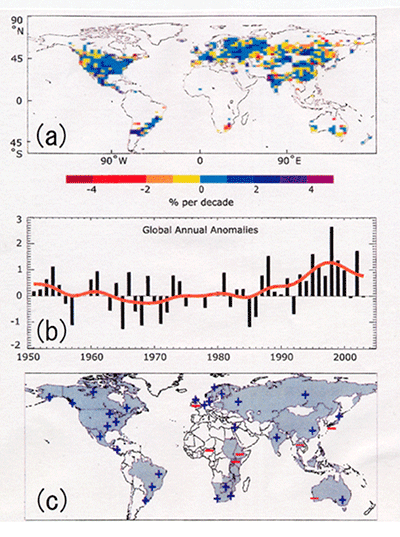
(図2)(a)非常に強い豪雨日の降水量が年降水量に占める割合(10年あたりの%)の長期変動傾向の分布。(b) 同上の割合(10年あたりの%)の長期変動。(1961-1990年の平均値からの偏差で示す)。(c)国別にみた最近数十年の豪雨の長期変化傾向。(IPCC, 2007による)
(図2)(c)は、地域性については(a)と、変化傾向については(b)と、同じような内容を示すが、国別にアミ(ねずみ色)をかけて、長期の変動傾向を示したものである。
降水日数・降水強度
(図3)に東アジア・東南アジアにおける(a)年降水日数、(b)年平均降水強度の1961年から2000年までの40年間における長期傾向を示す。 年降水日数の減少傾向はインドシナ半島北部、華北から西日本にかけて、きわだっている。年平均降水強度は、インドシナ半島北部、揚子江下流域、西南日本で増加している。
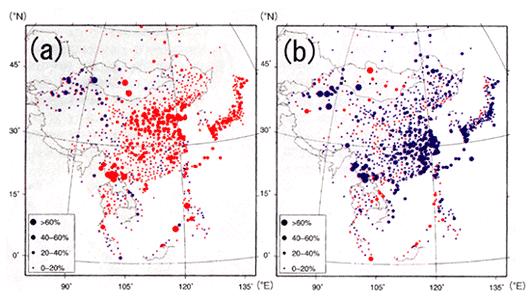
(図3)(a)年平均降水日数、(b)年平均降水強度の長期(1961‐2000年)の変化傾向。赤は減少傾向、青は増加傾向。(遠藤伸彦ほか、2007による)
以上のように、地域性は認められるが、全般的には降水日数は減少、しかし、降水強度は増加する傾向がみとめられる。従って、上に述べた年總降水量では長期傾向ははっきりしないが、豪雨は増加傾向にあることと合わせて、強い雨の異常気象が今後増加する可能性が大きいことに留意しなければならない。
大雨の再現期間
ここでいう大雨の再現期間とは、ある地点で、日降水量Xmm以上の大雨が平均してT年に1回の割合で起きると期待されるとき、「日降水量Xmmの再現期間はT年」、または、「再現期間T年の日降水量はXmm」と定義する。通常は年最大日降水量の長年の観測値を使って、統計学的に計算される。厳密にいうと、大雨が出現した年の再現期間を求めていることになるが、通常の目的にはこれで充分であろう。
かつて、気象庁の菊地原英和は、日降水量の大きな値に関する再現期間の研究を行った。その結果の一部を紹介する。(図4)は日本における再現期間10年の日降水量の分布で九州の西岸と東岸の一部、四国の南岸、紀伊半島の南岸、伊豆七島、関東の西部と北部山地に240mm以上の大きな値がでている。200mm以上の値は瀬戸内を除く西南日本のほとんど、東海道・関東のほとんどの地域を含む。
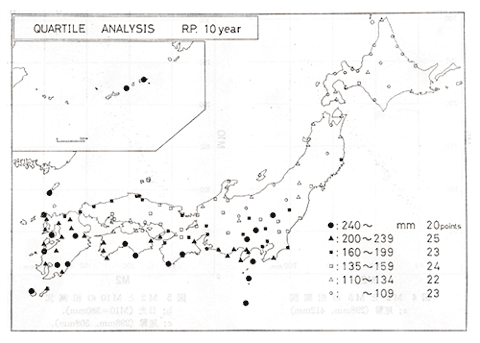
(図4)再現期間10年の日降水量(mm)の分布。(菊地原・鈴木による)
この分布を見れば、“台風の影響が強い地域である”と容易に想像がつくであろう。詳しく調べると、台風そのもの(台風圏内の気流)による場合が43%、台風は遠く南方洋上にあっても近くにある前線が活発化して発生した場合と、梅雨前線などの場合を合わせて約40%、残りは、温帯低気圧による場合が約17%であった。
このように台風以外の場合もあるので、北海道や東北地方でも、再現期間10年の値はかなり大きい。過去、日降水量の最大観測値170-180mm以上の値を北海道でも観測している。北海道の苫小牧では1950年8月1日に447.9mmの日降水量を観測したが、台風の直接の影響よりも強い前線活動の結果と考えられている。
最近はすでに述べてきたように強い雨が増加する傾向にあるので、ある年数の再現期間の日降水量は大きくなる。別の言い方をすれば、ある大きな日降水量の値の再現期間は短くなることが予想される。
異常豪雨の地点発生
(図5)は異常豪雨の発生地点の分布を示す。ここで異常豪雨の定義は『1位(極値)(x1)が2位 (x2) よりもどのくらい大きいか』とした。具体的な求め方は専門的になるので省略するが、異常豪雨を(A)とすると、
A=(x1‐x2)/ Sx
で求める。Sx は標準偏差で長年の平均値に対する偏りの大きさを表す。その地点がもともと変動が大きな地点の場合もあるので、標準偏差で割って基準化した。(図5)はこのAの値の分布である。Aが2より大きい地点(図中で星印)は興味あることに(図4)で大きな値を示した地域の北側((図4)の白四角・白三角・白丸)の地域に分布している。つまり、(図4)は非常に大きな極値(異常豪雨)がでる地点、(図5)は時折だが、2位より突出して大きな極値(異常豪雨)がでる地点を示していると理解される。
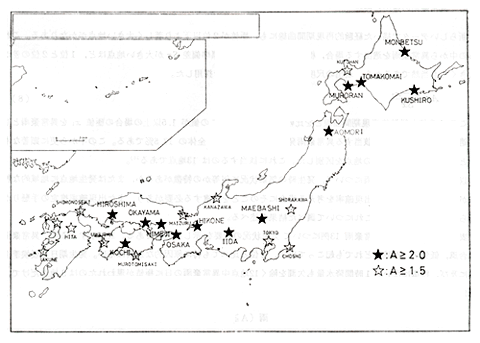
(図5)異常豪雨の発生地点の分布。(菊地原・鈴木による)
このような分布を示す理由は日本列島の形が関係していると思われるが、ここには、統計的な解析の結果を示すにとどめる。



