異常気象を追う
No.10
2008.07.30
吉野正敏
雷雨活動
雷は増えているか?
“雷が、近年、増えてきた”と感じている人が多い。むかしは、“雷が鳴ると梅雨が明ける”と言われた。しかし、この頃は梅雨中にも強い雨とともに雷が鳴り、梅雨が明けても雷を伴う激しい夕立が多い。
冬、日本海側では雪と雷が季節風の到来を告げる。 しかし雷は“一発雷”と言って、“ドン”としか鳴らない。そうしてまた、静寂にもどる。何か、物足ら ないような感じだが、これもこの地方特有の冬の風物詩であった。ところが、最近は“ドドーン”と鳴り、少しの間をおいて、2‐3発連続する。むずかしく言 うと、雷雨活動は活発化しているように思える。
今回は、異常な雷雨活動とは何か、最近の傾向はどうなのか、について考えてみたい。
雷雨活動とは
異常気象とみなされるような雷雨活動とはどのようなものか。このエッセイシリーズの筆者としては、答えに窮する。異常な雷雨活動の指標がはっきりしてい ないからである。気象庁の言葉では「発雷」があり、雷鳴、稲光、落雷など関係する現象の呼び名は、一般の人びともよく知っている。それならば、これらの現 象の回数が、ある時間内に多いことなのか、ある範囲(地域)内で多いことなのか、あるいは程度が強いことなのか。
言うまでもなく、雷雨活動とは雷雲からの降水活動(雨・雪・雹・あられなど)すべてを含むであろう。また雷雲(クラスター)の大きさ(直径・高さ)、一 定範囲(地域)内におけるクラスターの数、それらの寿命時間などにその特徴が現れるであろう。だから、例えば、「雷鳴の回数」だけで、雷雨活動の指標とす るには、むりがある。
気象学の専門家が使う指標にはショワルターインデックスや上層大気の不安程度を表す指標がある。雷雨の発生や活動の予測の指標に役立つが、上層の観測値は古い時代にはないし、多数の地点の観測値はないので、雷雨活動の長期変動の研究や、局地性の研究には使えない.。
日本海側の冬の雷
日本海側の雷の増加傾向を明らかにした研究(田中明夫、1997ほか)の結果を紹介しよう。冬(10月‐2月)の雷(発雷)回数を、1941年 ‐1970年の30年間と、1971年‐1997年(1998年)の17(18)年間を比較した。その統計結果を使って地域平均の雷日数を計算すると(表 1)のとうりである。
(表1)日本海側の地域別にみた冬(11月‐2月)の雷日数の変化
| 地方 | 1941‐1970年 | 1971‐1998年 | 増加 | 原資料の地点名 |
| 北海道 | 0.9日 | 1.9日 | +1.0日 | 稚内・寿都 |
| 東北 | 7.6 | 13.3 | +5.7 | 秋田・酒田 |
| 上越・中越 | 6.6 | 14.3 | +7.7 | 新潟・相川・高山・富山 |
| 北陸 | 8.6 | 17.8 | +9.2 | 金澤・輪島・福井・敦賀 |
| 山陰 | 3.1 | 8.8 | +5.7 | 豊岡・鳥取・西郷・松江 |
| 北九州 | 1.7 | 3.6 | +1.9 | 浜田・下関・福岡 |
この表から明らかなように、1970年前の30年間の平均と、1970年以降17(18)年間の平均を比較すると、北陸が最も顕著で、9.2日の増加、次いで、上越・中越の7.7日である。この大きな雷日数の増加は、もともと雷日数の多いところで、両者は直線関係である。
なお、この表には10月をいれてないが、北海道では10月に増加傾向は大きい。
どうして増加しているのか?
残念ながら、増加している理由をはっきりいえるような研究結果はない。いまのところ明らかにされているのは、“ある季節のある地点、またはある地域で”という条件つきで、雷の日数が増加していることの説明である。
例えば、秋田における高層の気温と雷日数の経年変化を調べた結果(工藤正哲、2001、気象庁研究時報、53、27‐35)によると、冬、地上気温の近 年の上昇傾向は+2℃/100年で統計学的に有意である。それに対し、下部成層圏(70、50、30、20、hPa面高度)の気温下降傾向は-4.0ない し-5.5℃/100年で統計学的に有意である。つまり、地上では温暖化し、下部成層圏では寒冷化しているのだから、大気の不安定度は増加の傾向にある。 このような統計学的に有意な寒冷化がみられるのは冬だけである。秋田上空の下部成層圏の状態はかなり広い地域的な代表性をもっていると思われ、地球温暖化 の影響を受けた下部成層圏循環型の変化傾向の結果だろう。しかし、どうしてそうなっているのかの研究はこれからである。また、(表1)で示したように、東 北地方の日本海側より北陸のほうが雷日数の増加傾向は強い。どうしてなのか、理由の解明はこれからである。
対流圏上部(300hPa)の気温下降傾向は春と秋が統計的に有意だが、冬は有意でない。このような、季節による差も今後の研究課題である。おそらく、雷の発生する気圧配置型の差なども関係しているように思われる。
世界的にみても増加しているか?
外国でも雷日数が増加しているという報告が多い。まずブルガリアにおける研究(Bocheva, L. et al., 2007)を紹介する。黒海の近くとはいえ、南ヨーロッパで夏に乾燥する大陸内部の例として参考になろう。ブルガリア国内67の観測所の記録から、 1961年-1990年の30年間と1991年-2005年の15年間とを比較した。その結果、4月から9月までの暖候期にはどの月も雷日数は増している が、特に、7, 8, 9 月が明瞭である。
国内全体をまとめてみると、季節平均の雷日数は21.5日から24.4日に増加した。これは約14%の増加である。一方、強雨日数は7.6日から 12.2日に増加し、約60%の増加である。(図1)は1961‐1990年の30年間と1991‐2005年の15年間の強雨日数と雷日数との比較であ る。強雨日数では5月下旬から近年の増加がめだっている。7月中旬は約4倍・7月下旬・8月上旬では約3倍になっている。これがみな雷をともなっていたか どうかは不明だが、非常な増加と言わざるをえない。このブルガリアの研究者達は“異常気象”とは言ってないが、私は異常気象と言ってもよいと思う。
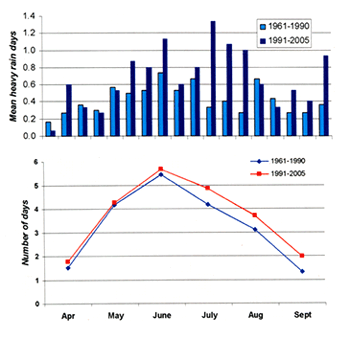
(図1)ブルガリアにおける強雨日数と雷日数の最近の増加傾向。 (1961‐1990年の平均)と(1991‐2005年の平均)の比較。 (上)旬平均の強雨日数、(下)月平均の雷日数。(L. Bocheva et al., 2007による)
二つ目の例として、オーストラリア南東部のアデレードとその東から南東方向170kmの範囲における6地点の調査結果(Davis et al., 2008, Aust. Met. Mag., 57, 1-11)を紹介する。1970年以降2004年までの雷日数の長期変化は、暖候期の始まりの10‐12月(南半球だから)に日数の増加傾向が統計的に有意である。雷日数のこの増加傾向と、地上気温、500 hPa 面高度の気温、大気不安定度の指数などとの相関関係を調べたが、地点により有意な関係をもつ対象が異なる。
これは雷雨が局地性にとむためと考えられ、乾燥地域における暖候期の雷雨活動の一般的な特徴とも考えられる。(表2)にオーストラリア南東部における雷雨日数の増加率を示す。
(表2)オーストラリア南東部における雷雨日数の増加率(日/100年) |
| 期 間 | レイヴァートン | ガンビア山 | ワガワガ | ミルドゥーラ | アデレード空港 | イーストセイル |
| 10月-3月 | 18.5* | 10.8* | 2.9 | 8.2* | 16.4* | |
| 10月-12月 | 11.0* | 6.4* | 1.0 | 5.6* | 11.4* | 8.1* |
| 1月-3月 | 7.6* | 4.2* | 6.3* | -10.4 | -1.5 | 9.2* |
注: * は95%で統計学的に有意 | ||||||
日本における調査結果と同じく、増加率はかなり大きい。 最大で18.5日/100年におよぶ。しかし、その局地性が大きく、すぐ近くにはその半分の増加率、あるいは、増加傾向が有意でない地点すらある。これはこれから解明してゆかねばならない。また、さらに興味あるのは、暖候期の前半(10月-12月)と後半(1月-3月)で傾向が逆転する地点があることである。これは雷雨発生の主な機構(熱雷であるか、界雷であるかなど)が前半の季節と後半の季節で異なることを意味し、日本の場合についても研究しなければならない。



