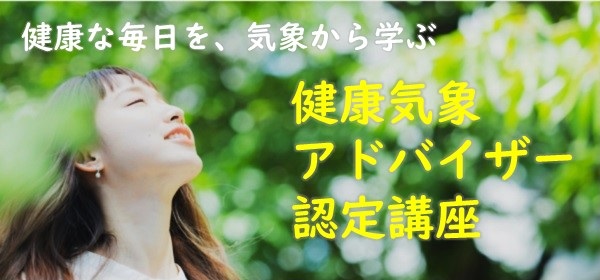お天気豆知識
No.90
2008.7 Categories垂直に発達する雲
積乱雲

(写真1)発達中の積乱雲
夏の午後、青空の中に上に向かって伸びたどっしりとした感じで、太陽に照らされて白く輝いた雲を見かけます。その雲は頭のほうがカリフラワーのようにボコボコしていたり(写真1)、朝顔の花が開いたようになっていることもあります。この雲が、雲の中で最も背が高く、ときには対流圏を使い切って、成層圏にも達することがある積乱雲です。学名はキュムロニンボス(Cumulonimbus)といいます。ラテン語の「積み重なる」を意味する“cumuls”と「雨雲」を意味する“nimbus”を組み合わせて作られた名前です。
積乱雲は上空に冷たい空気が入り、更に地面が日射で温められるなどで、上空と地面付近の温度差が大きいとき、つまり大気の状態が不安定なときに発生します。雲の中では激しい対流が起こっていて、幾つもの上昇気流があります。積乱雲を目の前にすると、小さな雲の固まりみたいなもの、セル(細胞)が上昇していくのを見ることができます。

(写真2)発達中の積乱雲とカナトコ雲
上に向かって成長した積乱雲は空気が安定した成層圏に達するとそれ以上は成長できず、雲は横方向に広がっていき、先の方は刷毛で掃いたようになっています。この部分が朝顔の花みたいな部分で、カナトコ雲と言います(写真2の奥の雲)。カナトコの部分は氷でできています。日本では夏でも上空は西よりの風が吹いているので、カナトコの部分は東方向に広がることが多いのですが、上空の風に比べて上昇気流が強いと積乱雲全体がきのこのような形になります。
日が沈むなどして上下方向の温度差がなくなると対流は弱まり、積乱雲は衰えてしまいます。そのようなとき、搭状の部分だけがしぼんでしまい、カナトコ部分だけが残されます(写真3)。
積乱雲が通過すると、大粒の雨が降り、短時間で強い雨が降ります。雹が降ったり雷が発生し、強い風が吹くこともあります。冬ならば強い雪が降ります。トルネードや竜巻も積乱雲によるものです。単独の積乱雲の大きさは数10㎞なので、遠くから見ると(写真4)のように雨が降っているのは限られた部分で、夏の雷雨ならばたいてい30分も待てば止んでしまいます。

(写真3)積乱雲の末期
(カナトコ部分だけ取り残される)

(写真4)積乱雲から降っている雨
登山中に積乱雲の中に入ってしまうと大変なことになります。回りはガス(霧)に覆われて視界がきかなくなり、大粒の雨が降り、雷も鳴ります。平地だと雷は上から来ますが、雲の中に入った山では横からの落雷もあります。特に岩の多い稜線を行動中に雷に遇うと隠れるところもなく大変危険です。昭和40年代ですが、穂高岳の岩陵を行動中の松本深志高校の生徒たちに落雷があり、死傷者が出ました。でも山で霧に包まれ雨が降り出してもそれが積乱雲によるものかどうかもわかりません。昔の山の気象の本を見ると、このような時に携帯ラジオにガーガーと雑音が入ると雷雲に包まれているので注意が必要だと書かれていました。
平成に入ってからは谷川連峰の沢で、上流に降った積乱雲による雨で沢が増水し、死傷者が出ています。そのときは事故が起こった沢の周辺で雨が降っていませんでした。川や沢の上流で発達した積乱雲からの強い雨が降ると、今居るところはたいした雨でなくても、しばらくすると急に水かさが増すことがあります。夏、川や沢で遊ぶときは気象情報に十分注意してください。