お天気豆知識
お天気雑談の記事一覧
No.14
2002.11 Categoriesその他
歴史をも動かす天気

毎日の生活で、天気が悪かったために予定どおり物事が進まなかったことは多々あると思います。例えば、旅行先で雨に降られ、すばらしい景色がよく見えなかったとか、傘を持たずに出かけたため、雨に降られて濡れてしまい風邪を引いてしまったとか、また子供の頃ならば、雨で楽しみにしていた運動会や遠足が中止になったことがあるかと思います。
今回は、一国の運命までもが気象現象により左右されたようなことをいくつか紹介します。
元寇来襲
元寇来襲と天気の関係は日本では有名な話ですね。モンゴル帝国5代皇帝フビライは中国の南宋や朝鮮の高麗をおさえた後、日本を支配下におこうとして、1274年(文久11年)10月と1281年(弘安4年)7月の2度、日本に来襲しています。鎌倉幕府の執権であった北条時宗は、九州方面に所領を持つ御家人により迎え撃っています。
戦法や軍備の違い、兵員の数などで日本側は劣勢でしたが、どちらも嵐や暴風雨により元軍は退却しています。日本に幸いした暴風なので、「神風」という言葉ができました。しかし、後世には悲しいことに使われました。第2次世界大戦では航空機に爆弾を積んで敵艦に体当たりをするという「神風特攻隊」が編成され、多くの若い命が散っています。
無敵艦隊の敗北
16世紀後半のことです。スペインはフェリペ2世、イングランドはエリザベス1世のときです。イングランドとスペインは根深い対抗関係が続いていました。16世紀前半にスペインが完全な制海権を持っていたカリブ海域にイングランド船が出没するようになり、スペインによるカリブ海支配が危うくなり始めていました。スペインは27,000名の兵員を載せた130隻の艦隊でイングランドの攻撃に向かいました。
しかし、嵐が5日間続き、スペイン艦隊はスコットランドの岩礁地帯で壊滅的な被害を受けました。その後スペイン艦隊はイングランド艦隊により撃破され、イングランドが海外貿易などで栄え、大英帝国と呼ばれるようになりました。
ワーテルローの戦い
ワーテルローの戦いは、一連のナポレオン戦争での最後の戦争です。この戦いは、1815年6月15日から18日の間に、現在のベルギーの首都ブリュッセルの南東にあるワーテルローで行われました。始めイギリス・オランダの連合軍がフランス軍を迎え撃っていました。17日午後からこの付近では雷雨が発生し、雨は18日まで続き、地面は沼のようになってしまいました。このため、フランス軍の侵攻速度は遅くなり、そこにプロイセン軍が攻撃を開始したため、フランス軍は敗退しました。この戦いでナポレオンが率いるフランス軍は敗北し、フランスによるヨーロッパ支配が終わり、ヨーロッパにおける新しい政治的・軍事的な勢力関係が確定しました。
地面が沼のようになったということですから、激しい雨が降り、雨量も多かったと思います。上空に強い寒気を持った、かなりの規模の低気圧が来て、そこに向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、発達した積乱雲が発生し、雷を伴った激しい雨が降ったと考えられます。
古代ギリシア哲学
イオニアのミレトスで生まれた古代ギリシアの哲学者タレス(Thales)はギリシア哲学の祖といわれ、ギリシアの七賢人の一人に数えられています。また、タレスは気象の知識を実際に応用した人物です。
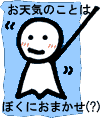
タレスは天気の変化傾向を注意深く観察し、ある夏のオリーブの実の作柄を予想し、周辺農園のオリーブの実を買い占めました。タレスの予想は当たり、莫大な富を得ました。おかげで、タレスはその後の人生をすべて哲学に専心したそうです。
凡人である筆者は、儲けたお金は遊行費に使ったり、生活費に当てたりですが、志を高く持った人は違います。
No.13
2002.11 Categories秋
帰ってきたサケ

(写真1)定置網から戻った漁船から水揚げされるサケ

(写真2)水揚げされたサケで埋まった魚市場
毎年10月末から12月上旬にかけて、三陸の各河川にはサケが産卵のために遡上してきます。筆者は岩手県釜石市に6年間住みましたが、毎年帰ってくるサケを川へ見に行くのが楽しみでした。釜石近辺にはさほど大きな川はなく、見に行く場所は河口近くなので、目の前で大きなサケが泳ぎ、必死に川を遡る様子を見ることができました。
右の(写真1/写真2)は岩手県下閉伊郡山田町の船越漁港にある魚市場にて11月中旬に撮影したものです。
三陸沿岸の海上にはあちこちに定置網があり、そこにもサケが入ってきます。定置網から戻った漁船からサケを水揚げしている場面に出会うと壮観です。水揚げされるサケが網から洪水のようにあふれ、市場内はたちまちサケでいっぱいになります。その後サケは雄雌に分けられて競りにかけられます。この時期、町の魚屋の店先もサケで占領され、他の魚は隅っこの方で肩身の狭い思いをしているようでした。
産卵のために帰ってきたサケは陸に近づくと餌を取らなくなり、雄は鼻の先が曲がってきます。銀色に輝いていた皮は黒っぽくなり、赤みがかった縞模様が現れます。腹には雌ならたくさんのイクラがあり、雄なら大きな白子が入っていますが、その身は油が抜け白っぽくなり、そのままで食べるには味が落ちてきます。
三陸地方ではこのようなサケを利用して、新巻鮭が作られます。作り方を紹介します。
- 胸鰭から尾鰭近くまで腹を開けて内臓を取り出し、中央にある骨の近くの血合い、エラを取り去る。
- 水洗いをした後、たっぷりと塩を擦り込む。そのときは尾から頭の方に向けて鱗に逆らって強く擦り込むのと、頭や目の部分の塩をきつくするのがコツ。
- 腹の中にたっぷりと塩を擦り込み、容器に入れて軽い重石をし、日が当たらぬ涼しいところで1週間ほどおく。
- その後水洗いをして余分な塩分を取り去る。
- 頭部を縄でくくり、腹の部分に割り箸を入れ、腹の中もよく乾くようにして2日から3日ほど干す。
このようにしてできあがった新巻鮭を切り身にして焼くと、薫製のような独特の風味があります。新巻鮭は各家庭でも作られますが、水産加工会社などでは大量に作るためそれを干す様子は、まさにサケのすだれです。
この時期は乾燥した西風が吹く日が多くなり、寒さも日に日に増していきます。このような天候が美味しい新巻鮭を作るのに役立つのですが、日に日に増す寒さはやはりこたえます。何かと忙しい初冬に暖かいと動きやすいし、暖房費も助かります。釜石に住んでいる間に、暖かい初冬の年もありました。暖かいので毎日の生活は楽でしたが、このような年の新巻鮭の味はイマイチのように感じました。
今年の10月は秋がどこにいったのだろうという感じでしたが、11月に入ったとたん連日のように冬型の気圧配置の日が続いています。毎日の天気予報でも「12月なみの寒さの日になります。」といっているのを耳にします。極端な寒さはごめん被りたいですが、寒い時期に寒くならないのも、よい新巻鮭ができないなどの影響が出てくるかもしれません。冬は寒いから冬なのですね。
No.2
2002.8 Categories夏
夏と日本の伝統家屋
毎日暑い日が続きます。「最高気温が人間の体温に近い35~36℃」というニュースや天気予報を聞くと、よけいに暑く感じます。日本で気象観測が開始されてからの最高気温は、1933年7月25日山形市での40.8℃でしたから、これから比べるとまだましといえるでしょう。

ところで、江戸時代の川柳にこのようなものがあります。
寝ていても団扇(うちわ)の動く親心
(渡辺信一郎著「江戸川柳」岩波書店より)
乳を飲んで寝込んだ赤子に添い寝している母親もウトウトとし、それでも赤子にたかる虫を寄せ付けないようにと、手にした団扇だけは扇ぎ揺らせているという光景で、赤子に対する母親の気遣いの様子が描かれています。それとともに、赤子に風を送り涼しくしているとも考えられます。
現代のように電気がなく、冷房設備が無かった頃は、涼をとるのには風が重要な役割をなしていました。人間は、「1mの風が吹くと、気温より1度寒く感じる」といわれています。夏の暑い盛りでも風をうまく取り入れれば、涼しく過ごせることは想像できます。

菅沼にて吉野正敏撮影(1974年10月13日)
花岡利昌著「伝統民家の生態学」(海青社)には、岐阜県の飛騨高山市内にある吹き抜け櫓(やぐら)を持つ伝統民家での気温や風の調査結果が載っています。岐阜県高山市は飛騨盆地の中央にあり、日最高気温の平均値は8月が最高で30.1℃、1月が最低で3.0℃です。年間の気温較差は27.1℃となり、夏の暑さと冬の寒さはかなりきびしいことがわかります。
民家には、夏の暑さを緩和するために吹き抜け櫓を生かして各部屋とも空気が流れやすい構造となっています。測定が行われた日は、高山測候所の観測記録によると、天気は晴れで、日中の最高気温は30.5℃、湿度は68~79%と蒸し暑い日でした。日中の戸外の平均気温は28.6℃ですが、室内の平均気温は26.5℃となっており、暑さが緩和されているとしています。
叫内米子氏の調査によると、気流と気温の体感に及ぼす効果の実験によれば、気温25℃で快適とする風速は0.4~1.0m/s、30℃では0.6~1.0m/sの範囲にあるという結果になっています。この日の室内での風の測定値は、快適とする範囲におさまる結果となっていました。
話は変わりますが、能登半島北部内陸にある中谷家(石川県柳田村)を訪れたときのことです。中谷家は江戸時代能登にあった天領の1つ、柳田の黒川村を任された庄屋です。堀と塀と庄屋門がある豪農のお屋敷で、朱と黒の漆で塗り分けられた総漆塗りの土蔵が有名です。母屋は江戸時代前期に建てられました。風通しの良い構造となっていて、囲炉裏のある部屋は高い天井となっていました。
ちなみに、輪島測候所のデータによると、日平均最高気温は8月が最も高く29.3℃、2月が最も低く5.9℃です。データからみて高山ほどではありませんが、冬は寒さの厳しい地域です。江戸時代の暖房といえば火鉢やコタツですから、案内して下さった方に「寒くなかったのですか。」とお尋ねしたところ、「日本の夏は暑く皮まで脱ぐわけにいかないが、冬は寒ければ着ればよい。」との答えが返ってきました。まさにおっしゃられるとおりです。夏は暑いものなのです。度の過ぎた暑さはかないませんが、「寒さの夏はおろおろ歩き……(宮澤賢治 雨ニモマケズの一説)」よりいいでしょう。
※高山と輪島の気象データは気象庁作成の平年値を使用しました。



